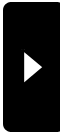防犯面・利便性・ライトアップ・安全性においてセンサーライトは役立ちますが、とくに防犯対策に有効です。正面玄関・門扉・駐車場・側道・裏側などにつければ、侵入者を撃退する効果と、近所の人が侵入者に気づく効果が得られます。
●光で人の存在を周知する
センサーライトが点灯することで、住人、近隣住民、通行人などが不審者や侵入者の存在を認識し、早期の避難・通報に役立ちます。
●侵入者を光で牽制する
センサーライトが明るく照らすことで、侵入者は「見つかる、通報される」という気持ちを抱き、犯罪行為を牽制、侵入や窃盗の被害を未然に防止する効果が期待できます。
●見通しが悪い場所を明るく照らす
暗い場所や見通しの悪い場所を明るく照らすことで、暗闇で発生する可能性のあるさまざまな不審行為(下見など)の防止効果が期待できます。

センサーライトの電源タイプは、主に3種類ありますが、後付けの場合はソーラータイプがおすすめです。
●乾電池タイプ
乾電池さえあればコンセントの有無を問わず設置できるメリットがあります。ただし電池切れによって動作しなくなるため、こまめに電池交換を行うことが大切です。消費電力の少ないLEDライトを採用したセンサーライトがおすすめです。
●電源タイプ
コンセントから給電を行うため、停電さえ発生しなければ常に動作する点がメリットです。ただし、電源を取れる箇所が近くになければコンセント増設の必要があるなど、工事に手間がかかることがあるという点がデメリットです。
●ソーラーパネルタイプ
太陽光で発電・充電を行うソーラーパネルを搭載しているため、電池を交換する必要がなく、コンセントに繋ぐ必要もないというメリットがあります。ただし光が当たらなければ発電・充電を行わないため、悪天候が続くと思った通りに動作しない可能性があります。
そして、防犯目的でセンサーライトを設置する際は、防犯効果と動作性に配慮して設置場所を決めることも大切です。
風で樹木などが揺れたり動いたりしない場所、犬・猫などの動物が通らない場所、道路を通行する人や車両に反応しない場所を選ぶようにしましょう。また、センサーライト自体が揺れないようにしっかりと固定することも重要です。
取り付けは、壁に穴を開けずに簡単に後づけできる、強力両面テープを使うことがほとんどです。なかには、雨どいやカーポートの柱など両面テープがつきにくい場所にも設置しやすい、バンドで取りつけられる商品もあります。
電池交換のとき、故障したとき、交換するときのことを考えて、メンテナンスに手間取るような高所への設置は避けたほうが良いでしょう。
ご自宅にぴったりのセンサーライトを選んで、しっかり防犯対策をしましょう


参照)
ポーチ・勝手口・門柱のあかり | 商品一覧 | LED照明器具(シーリングライト・デスクスタンドなど) | Panasonic
センサーライトの防犯効果とは?選び方と屋外に設置するポイント|HOME ALSOK研究所|ホームセキュリティのALSOK
















 続けて入浴することで浴室内が冷えることもなく、追い炊きも不要で省エネになります。さらに、家族の入浴後はドアを開け、浴室の湿度で家中を加湿するのも良いでしょう。小さな工夫で意外に省エネできるものです。
続けて入浴することで浴室内が冷えることもなく、追い炊きも不要で省エネになります。さらに、家族の入浴後はドアを開け、浴室の湿度で家中を加湿するのも良いでしょう。小さな工夫で意外に省エネできるものです。











 目的別にご紹介していきましょう
目的別にご紹介していきましょう